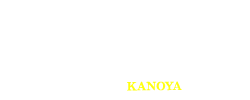オヤジの朝は早い。一人の早朝、コーヒーを淹れ朝刊に目を通すのがルーティーン。今日は新聞の前に、テーブルの上に置かれていた息子の同窓会報が目に入った。「最終号」と記されたその表紙に目を通した。近々隣の高校と合併するから、これが最後ということだろう。寄稿文は、卒業生で今は有名なミュージシャンとなった人のもので、卒業後、暫くぶりに訪ねた下車駅から校舎までの通学路のことが書かれてあった。街並みが変わり、嘗て利用したお店が消え、そこに居た人も居なくなった。でもそれを嘆く必要は無い。自分も周りも全てが移ろいゆく。そのことを胸にこれから先を楽しもう。と、綴られていた…。読み終えると新聞の一面に目をやった。”女性初の総理誕生”の文字が目に飛び込んできた。「時代は変わった」と実感した。
義父が亡くなり、三週間が経とうとしている。満90歳の天寿を全うし、義母や子どもたちに看取られての最期だった。義父とは妻と結婚してからの付き合いだが、実父を早く亡くしたオヤジにすれば義父と過ごした時間の方が長くなった。義父も17歳で父親が急逝し、当時通っていた高校も定時制に編入を余儀なくされ、家業の製菓業を後継して母親と四人の妹を養った。「好きな油絵を描くことが心の拠り所だった」と、生前に聞いている。結婚し二人の子供を養うために光学レンズ加工の仕事も始め、オヤジが初めて訪ねた時にもレンズを磨く工作機械が音をたてていたのを今でも思い出す。画作は途切れること無く続けられ、国内外の絵画展で多くの作品が入選・入賞を果たし、フランス芸術家協会(ル・サロン)の永久会員にも登録された。明るく温厚な人柄で、風景画や花の絵などの作品にもその”明るさ”が表れていたように思う。絵を描く事への情熱は絶えること無く、亡くなる直前まで筆を握っていた、と聞く。
去年の今頃、義父母と妻を伴って木曽開田高原に紅葉狩りに出かけた。全山が赤や黄色に染まり、殊に唐松の葉が金色に輝いていた光景を、自然をこよなく愛した義父の「いいものを観せてもらった。感動した。」の言葉と共に想い出す。帰宅後一週間絵を描き続けた…。とも聞いている。
「過去を振り返ることはしない。先を見据えて今を生きる」と、生前義父が良く口にしていた、オヤジも共感する言葉だ。今回この文章を書いたのは、今をよく生きこれから先を楽しむために、敢えて、生き方に影響を受けた義父との時間を記しておきたいと、思ってのことである。”全ては移ろいゆく”かもしれない。時代の変化に対応することは、好むと好まざるとに関わらず必要だ。商売をやっているからか、それは凄く感じる。しかし、大切にしたいこと、「精神」は受け継がれてゆく。